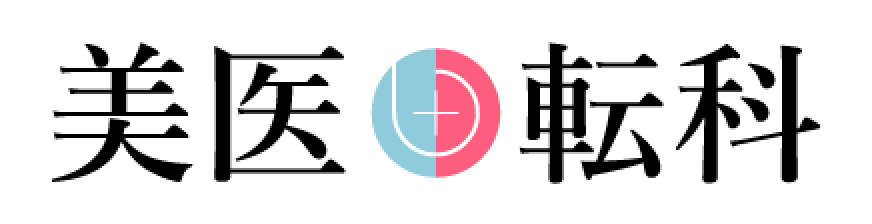美容クリニックの集患目的のはずがバズ狙い?美容外科医が陥りやすい不適切なSNS投稿事例まとめ
更新日:
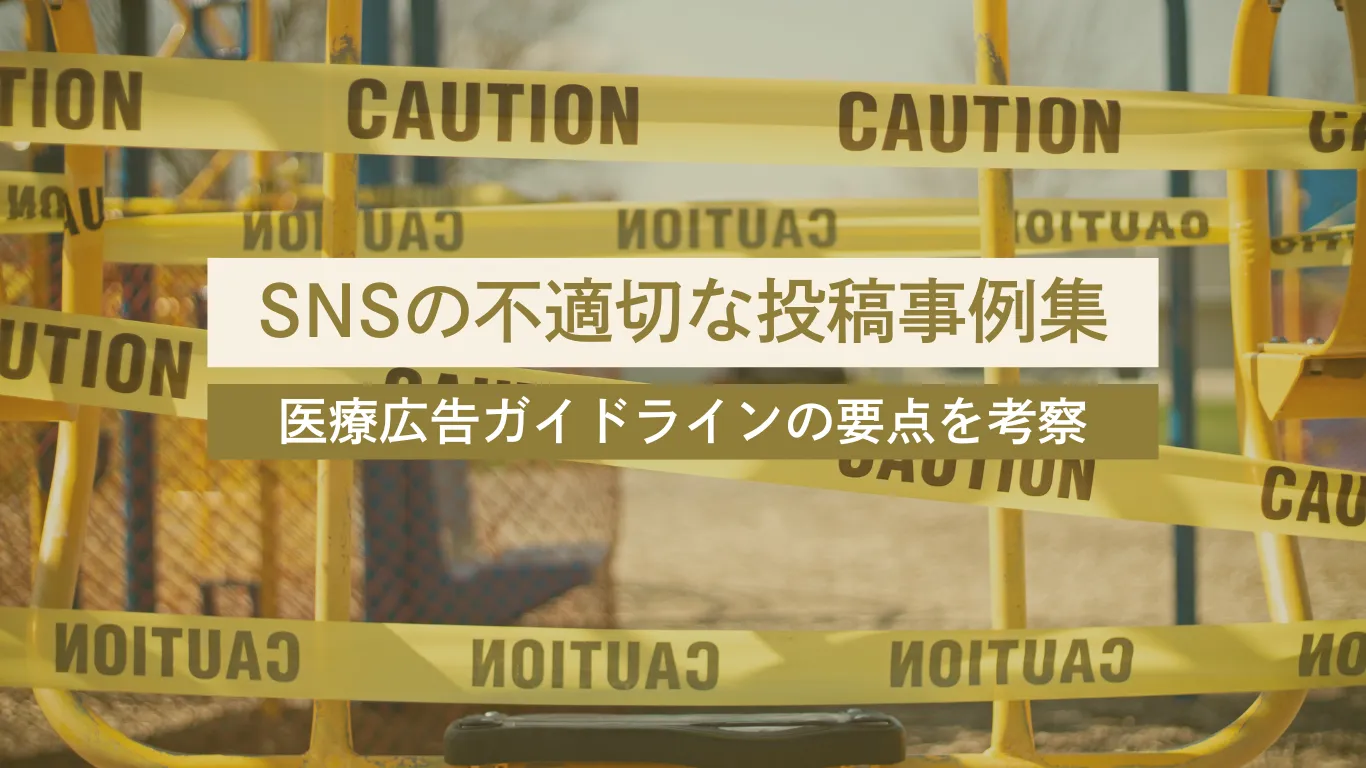
美容医療業界では、SNSを活用した集客がますます盛んになっています。多くの美容外科医が自身の施術結果をシェアし、患者様の関心を引くために様々な手法を用いています。しかし、注目を集めることが目的となってしまい過剰な演出や不適切な投稿が、倫理的な問題や法的リスクを引き起こすこともあります。
この記事では、これらの不適切な投稿事例を取り上げ、患者様との信頼関係を守るためにおさえておきたい医療広告ガイドラインの要点について考察します。
多くの美容クリニックがSNSを用いて集患する理由
多くの美容クリニックがSNS発信に力を入れている理由は、いくつかの要因に基づいています。特に、SNSの特性が美容医療業界にとって非常に有利に働くため、積極的な活用が進んでいます。以下にその主な理由を挙げます。
ターゲット層への直接的なアプローチ
SNSは、特定のターゲット層に向けた広告や情報発信が可能なため、美容外科医にとって非常に効果的なツールです。
特に、美容医療に関心のある20代から40代の女性層はSNSを頻繁に利用しており、この層に向けた宣伝や情報提供を行えます。
インスタグラムのビジュアル重視のプラットフォームでは、施術結果や症例写真をシェアすることで、視覚的にアプローチが可能です。
ブランド認知の拡大
SNSは低コストで広範囲にリーチできるため、美容外科医のブランド認知を急速に広げられます。広告予算を大きくかけずとも、魅力的なコンテンツをシェアすることで、短期間で多くのフォロワーや潜在的な患者様にアプローチできます。
特に、美容外科のように結果やビジュアルが重要な業界では、施術前後の写真や動画を活用して、信頼感や実績を積み重ねられます。
口コミ・レビューの確認
SNSはユーザー同士のつながりが強く、口コミの影響力が大きいです。患者様が施術後に体験をシェアしたり、他の患者様のレビューを参考にすることが多いため、SNSでのポジティブな口コミや体験談が集客に直結します。
また、フォロワーのリーチによって、一度シェアされた投稿が拡散されることで、無料で宣伝効果を得ることが可能です。
美容外科医個人への信頼を高めるため
SNSは医師やクリニックが自らの専門性や実績を公開する場としても有効です。症例写真や患者様の体験談を共有することで、医師の技術力やクリニックの信頼性をアピールできます。
さらに、医師が自身の意見や考えを発信することで、患者様との信頼関係を築きやすくなります。患者様がSNSを通じて医師の人柄や考え方に触れることで、実際に訪れる決断をしやすくなります。
競争優位性を高めるため
美容医療業界は競争が激しく、他院との差別化が求められます。SNSをうまく活用することで、他院との差別化を図り、患者様にアピールすることが可能です。
ユニークな施術方法や実績をシェアすることで、特定のニッチな市場に対して強い印象を与え、競争優位性を高められます。
インフルエンサーとのコラボレーション
SNSではインフルエンサーとのコラボレーションも非常に効果的です。美容外科は、人気のインフルエンサーと提携し、施術を体験してもらい、その体験をフォロワーとシェアしてもらうことで、短期間で多くの潜在患者様にリーチできます。
特にインフルエンサーが実際に体験した結果を公開することで、信頼性が高まり、クリニックへの訪問や予約につながりやすくなります。
本来の集患目的を履き違えた不適切なSNS投稿事例
SNSでの不適切な投稿事例として、以下のいくつかの点が挙げられます。
これらを踏まえ、無意識に自身も投稿していないか、どのように改善すべきかを具体的に見ていきましょう。
症例写真の過度な加工
一部の美容外科医が、症例写真を過度に加工して施術効果を誇張する事例があります。
例えば、施術前後の写真を修正して、効果を過剰に強調したり、自然な肌のトーンやラインを美化するために色味や明るさを変えたりすることがあります。他には加工アプリで印象を操作した症例写真をそのまま掲載する事例も出ています。
これにより、患者様は実際の施術結果と大きなギャップを感じ、期待外れに終わる可能性があります。
効果を保証するような断定表現
一部の美容外科医が、SNS投稿で施術の効果を過度に誇張し、「絶対に腫れません」「100%満足いただいてます」「永久持続」など、断定的な表現を使うことがあります。こうした表現は、施術の結果が個々の患者様によって異なることを無視した誤解を招き、患者様に過度な期待を抱かせます。
また、 医療広告ガイドラインでは、“確実性”や“効果の保証”を連想させる表現は禁止されています。医学的には個人差があり、結果を保証することは不可能なため悪用事例といえます。
麻酔後の膨張状態をビフォー写真として使用
美容外科医が、施術前に麻酔を施した後の膨らんだ状態を「ビフォー写真」として使用することがあります。麻酔によって体が通常より膨らむことは、手術の直後に見られる一時的な反応であり、実際の結果とは大きく異なります。これを「ビフォー」として使うことで、患者様が術後の状態と誤認し、施術後に実際の結果が異なることに対して不満を抱く原因となります。
このような手法は、SNSで一時的な注目を集めるかもしれませんが、長期的には患者様からの信頼を失う原因となり、法的なトラブルを引き起こす可能性もあります。
医師の経歴の誇張や専門医資格の自作自演
一部の美容外科医は、自身の経歴を水増ししたり、「〇〇認定専門医」などと活動実態のない専門医資格をSNSで誇張したり、虚偽の情報を記載することがあります。
例えば、実際には持っていない資格を「取得した」と主張したり、経験年数を水増しして「豊富な経験を持つ医師」と見せかける場合があります。また、特定の学会に所属していないにもかかわらず、「○○学会認定医」といった表現を使うこともあります。
このような自作自演の行為は、患者様の安全や業界全体の信頼性に重大な影響を与えるため、医師としての倫理を守り、正確で透明な情報を提供することが極めて重要です。
“バズる”を狙いモラルが破綻した手術事例
一部の美容外科クリニックが、SNSで注目を集めるために、極端な手術結果や不適切な施術後の演出を行うことがあります。その一例として、搾取した脂肪をニコチャンマークの形に見立てるというような、非常に不謹慎で不適切な手法が報告されています。
このような手法は、バズを狙って患者様の身体から取り出した脂肪を遊び心やパフォーマンスとして利用するものであり、モラルが完全に破綻しています。
美しさの考えを押し付ける心理的圧を与える投稿
一部の美容外科医がSNSで行う投稿は、特定の「美しさ」を過度に強調し、フォロワーや患者様にその基準を強制的に押し付けることがあります。
例えば、「真の美しさとは○○のような顔」「美しさは整形によって得られる」というメッセージが頻繁に投稿され、見た目や外見に対する過度なプレッシャーを与えることがあります。
このような投稿は、フォロワーに対して「自分もその美しさを手に入れなければならない」と感じさせ、心理的な圧力をかけることになります。
オペ中のインスタライブ
一部の美容外科医が、施術中にインスタライブで手術の様子をリアルタイムで配信する事例があります。
このような投稿は、手術をエンターテイメント化し、患者様のプライバシーを完全に無視した行為として問題視されています。
ライブ配信中に患者様の顔や体の詳細が映し出され、患者様本人の同意がない場合、重大なプライバシー侵害に繋がります。
医療広告ガイドラインに基づく正しい投稿方法
美容クリニックのSNS投稿は、医療広告ガイドラインに基づいて行う必要があります。これにより、患者様に対して正確で信頼性の高い情報を提供できるだけでなく、法律的なリスクも避けられます。
以下では、SNS投稿時に留意すべき医療広告ガイドラインの要点について、それぞれ解説します。
▼参考
No.1表記の根拠
「No.1」という表記を使用する場合、その根拠を明示する必要があります。例えば、「業界No.1の実績!」といった表現を使う場合、客観的な証拠やデータが求められます。
根拠を示さずに「No.1」を表記すると、虚偽の情報を提供することとなり、消費者に誤解を与えるリスクがあります。信頼性のある実績に基づいた表記を行うことが重要です。
実績やデータに基づいた「No.1」の表記を行い、その根拠を明確に伝えることが求められます。
実際のクリニックで得られた症例数、データ集計期間、データを取得した院名を明記して具体的な数値を示すようにしましょう。
症例写真にリスクや副作用の明記
症例写真を使用する際、施術に伴うリスクや副作用についても明記することが義務付けられています。
施術の効果を示すだけでなく、そのリスクや副作用についても正確に伝えることで、患者様に十分な情報を提供し、安心して選択できる環境を提供します。これにより、不安や誤解を避けられます。
症例写真に加えて、施術のリスクや副作用についても説明を加え、患者様が施術内容について十分理解できるようにしましょう。
誇大表現の禁止
施術の効果について過剰に誇張する表現は避けるべきです。
「○○術は変化量が乏しく、安全性が低いので、当院が新たに開発した○○術がおすすめです」などの表現は、医学的根拠を示していないにもかかわず、患者様に不正確な期待を抱かせる可能性があります。
誇大表現を使用すると、消費者に過剰な期待を与え、現実とのギャップから信頼を失うリスクがあります。施術は個人差があり、すべての患者様に同じ効果が現れるわけではありません。
施術の効果については、現実的かつ正確な表現を心掛け、過度な誇張を避けるようにしましょう。期待される効果の範囲についても説明を加え、患者様が納得できるように配慮します。
比較優良表現の禁止
「当院は県内一の症例数を誇ります。」などと他のクリニックや競合と比較して「当院が一番優れている」といった表現は控えた方が良いでしょう。
他院と比較して優位性を強調することは、他者を不当に貶めることに繋がりかねません。患者様に対して過剰な優越感を持たせることなく、当院の特徴を正確に伝えることが大切です。
自院の強みや特長を伝える際には、他院との比較を避け、独自の特色を強調することが望ましいです。患者様に対して透明性を持って、自院のメリットを説明しましょう。
治療効果を約束する表現の禁止
「絶対に成功する」「100%効果が出る」といった効果の約束は避けるべきです。
効果を約束する表現は、患者様に過剰な期待を抱かせ、結果として不満を招く可能性があります。施術には個人差があり、すべての患者様に同様の効果が得られるわけではないことを理解しておく必要があります。
施術の効果については、個人差があることを明記し、過剰な期待を与えないようにしましょう。また、施術後の経過や期待できる効果を現実的に伝えることが大切です。
治療効果に対する患者様の主観に基づく体験談の提示の禁止
患者様の体験談を基にした「治療効果があった」といった表現は慎重に行うべきです。
この場合、治療の効果以外のクリニックの接客の感想に対する体験談は提示できます。
治療効果に対する体験談は個別のケースに過ぎないため、他の患者様にも同様の結果が期待できるわけではありません。過度に強調すると、患者様に誤解を与え、信頼を損ねる恐れがあります。
体験談はあくまで一例として提示し、結果に個人差があることを伝えることが重要です。また、体験談を使用する場合は、患者様の同意を得た上で行うことが求められます。
まとめ
美容クリニックの集患におけるSNSの適切な運用は、患者様の信頼を得るために非常に重要です。
しかし、誇張されたビフォーアフター写真や無断使用された患者様の写真、過度な煽り表現など、広告の内容に不適切な要素が含まれる場合、法的なリスクや患者様の信頼喪失を引き起こす可能性があります。
これにより、クリニックの評判が悪化し、最終的には集患に悪影響を与えることになります。
医療広告ガイドラインに基づき、誇張表現や無断での写真使用、過剰な効果の約束は避けるべきです。患者様に対して正確で透明性のある情報提供を行うことが、信頼の獲得に繋がります。
また、広告における誤解を招く表現や過度な煽りは、患者様を不安にさせ、結果的にトラブルを引き起こすリスクを高めます。
SNSを活用する際は、規制を遵守し、倫理的な観点からも患者様の立場に立った広告を心掛けることが大切です。
これにより、長期的に安定した集患が可能となり、クリニックの信頼性を確保できます。