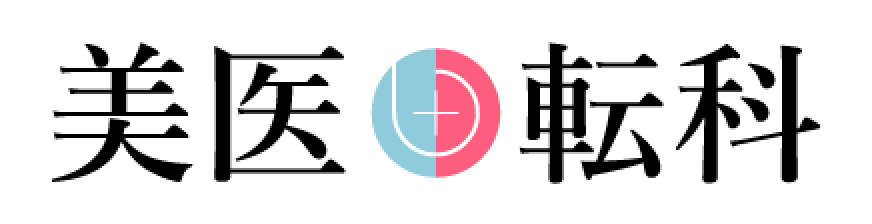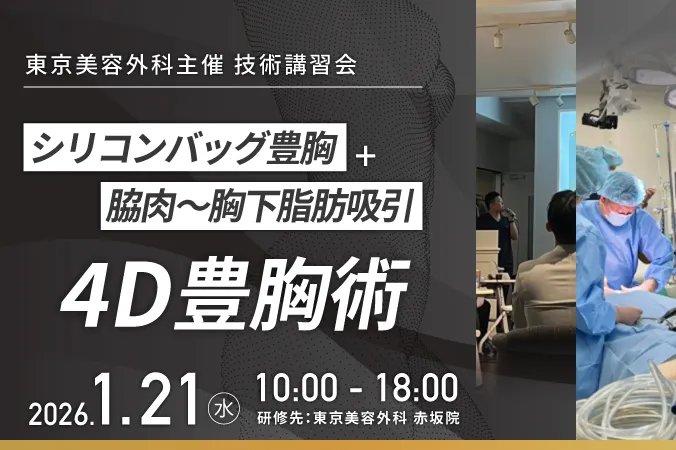転職に必要な「情報リテラシー力」とは?
更新日:

「まさか、自分がそのような理由で処分を受けるとは……」
入社して間もなく、真面目に業務に取り組んでいたにもかかわらず、ある日突然、上司から呼び出され、始末書の提出を求められる事態に直面した──。
こうした“思わぬトラブル”が、情報漏洩や職務規程違反として、個人のキャリアに影響を及ぼすケースが増加しています。
現在、企業が採用において最も警戒しているのは、「情報を適切に管理できない人材」です。
そして、そのリスクは特別な知識の欠如によるものではなく、日常の些細な行動の積み重ねから生じることが多いのです。
本稿では、実際に発生した事例をもとに、「特に注意すべき」情報リテラシーの基本を解説いたします。読み終える頃には、皆様の「面接通過力」と「信頼力」が確実に向上していることでしょう。
事例で学ぶ!やってはいけない情報管理ミス
事例1:「自宅で仕事しようとしただけ」で懲戒処分に!?
IT企業に入社したばかりの営業社員。
「家でも仕事を進めたい」と顧客リストを私物PCにコピーし、自宅で作業していました。
ところが、そのPCがマルウェアに感染。
顧客情報が外部に漏洩し、会社は謝罪・損害賠償・システム改修に追われる事態に。
彼自身も減給・出勤停止、さらには試用期間中での契約終了という厳しい結果を迎えました。
教訓:会社の情報は、会社の端末でしか扱わない!
事例2:社用携帯でSNS?甘く見た代償は“査定停止”
社用携帯にLINEやInstagramを入れ、休憩中に私用で使っていた20代社員。
通話履歴から私的利用が発覚し、1週間の出勤停止と査定評価の凍結処分を受けました。
本人は「仕事に支障はなかった」と主張しましたが、会社の判断は明確。
「社用携帯は資産であり、私的利用は職務規定違反です」。
教訓:社用端末は“公私混同NG”。私物とは完全に分けること!
事例3:何気ないSNS投稿が企業の信頼を壊す!?
「今日は大手◯◯社と打ち合わせ。緊張した〜」
そんな軽い気持ちのX(旧Twitter)投稿が、思わぬ炎上に。
投稿を見た取引先から「なぜ会議内容をSNSで漏らすのか?」とクレームが入り、社員は減給処分、会社は広報対応に追われる羽目に。
教訓:「社名・仕事内容」はSNSに書かないのが鉄則!
なぜ今、企業は“情報リテラシー”を重視するのか?
現代のビジネスにおいて、何よりも重要なのは「信頼」です。
どれほど優秀でも、たった一度のミスが顧客の信頼、会社のブランド、チームの絆を一瞬で壊すことがあります。
そのため多くの企業は、入社直後から情報セキュリティ教育を徹底。
オンライン研修や端末利用テスト、違反時のペナルティまで、「教えるだけでなく、守らせる」仕組みづくりを進めています。
人材紹介会社として伝えたいこと
マッチングの先にある“信頼”を意識して
私たち人材紹介会社の使命は、単に「企業と人をつなぐ」ことではありません。
入社後に安心して活躍できる“信頼される人材”を送り出すことです。
企業が求めているのは、スキルよりも「安心して任せられる人」。
そのため、私たちは面談時に以下のような点も確認しています。
セキュリティ意識や過去のトラブル対応経験
規則に対する姿勢や慎重さ
チームメンバーとしての自覚
一方で、求職者側にも意識が求められます。
応募前に企業の情報管理方針や職務規定を確認し、
「この会社の一員として信頼を築けるか?」を考えることが、採用後の活躍に直結します。
選考を有利に進めるなら
「知っていた」だけじゃ足りない。「守れる人」が選ばれる時代
ルールを理解しているだけでは、信頼は得られません。「誰も見ていなくても守れる人」こそが、今の時代に求められる人材です。
SNSやテレワークが日常化する中で、情報の境界はどんどん曖昧に。
だからこそ、「これくらいなら大丈夫」をやめて、日々の小さな行動を見直すことが、自分のキャリアを守る最大の防衛策になります。
まとめ
情報漏洩や職務規定違反は、多くの場合、悪意ではなく“無意識の行動”から生まれます。だからこそ、日々の業務の中で「これは本当に適切か」を立ち止まって考える姿勢が欠かせません。社用端末は会社の大切な資産であり、私的利用は厳禁です。また、SNSは誰でも簡単に発信できる便利なツールである一方で、その影響力の大きさゆえに、企業情報を不用意に発信することは重大なリスクにつながります。
さらに、企業だけでなく求職者にも「信頼される姿勢」が求められる時代です。採用の先にあるのは、共に信頼を築き合える関係。私たち人材紹介会社も、単なるマッチングではなく、入社後に安心して活躍できる“信頼の質”を重視することがますます重要になっています。
選考対策もお任せください